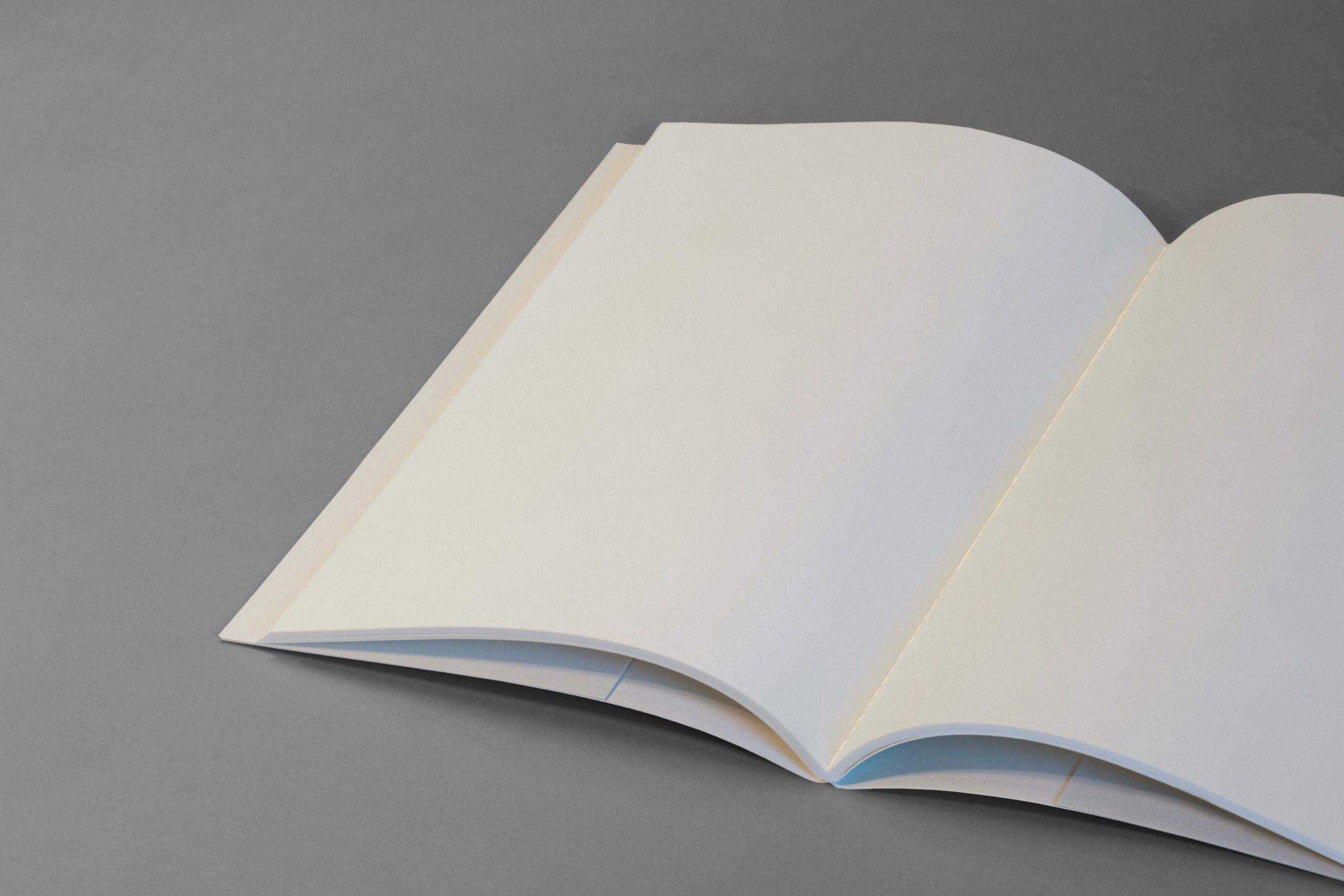石川さんが連載されている全倒ネット関東地区研修会のパネルディスカッションをまとめた「初めての法人破産申立」の第6回で、法人の破産申立ての時期について触れられています。
最近、法人の破産申立ては受任後直ちに行うべきであって、受任通知を送ることは不適切である、という議論が見られます。
このテーゼは、ときには正しく、ときには正しくない、と考えています。
つまり、このテーゼを絶対化はできず、事案の性質ごとにあてはまる場合もあてはまらない場合もあるということです。
そもそも、破産申立ての依頼者は、破産しようとする法人やその代表者です。
依頼を受けた申立代理人としては、依頼者の利益を第一義に考えるべきです。
では、破産申立てにおける依頼者の利益とは何でしょうか。
それは、混乱を引き起こさずに債務を整理し、個人であれば免責を得て経済生活を再生すること、法人であれば円滑な清算を行うことでしょう。
そのためには、依頼者が倒産秩序に反する行為を行って免責が得られなくなったり、破産犯罪に問われたり、役員責任を追及されたりないようにする必要があります。
つまり、申立代理人としては、この文脈で、債権者平等を図り、破産財団の保全を図ることが必要だということです。
また、破産申立てに当たっては、回収が不可能となる破産債権者らに対して衝撃をあたえることになるわけですが、不用意な行動によって混乱を生じさせ、依頼者に物理的または心理的な負担をかけさせないことも重要です。
まず、債権者平等を図り、破産財団の保全を図るためには、偏頗弁済や財産の散逸を防ぐ必要があります。
依頼を受けた時点で通常の営業を続けている会社では、回収未了の売掛金や、在庫商品などが残っていることが普通です。
これら売掛金や在庫商品は、時の経過とともに換価が困難となり、価値が劣化していきますので、速やかに破産を申し立て、破産管財人に引き継いでこれらの換価作業に早期に着手してもらうことが肝要です。
そのためには、受任通知を送って債権調査票の提出を待つなどということは、単に不要であるだけでなく、上記のような取付け騒ぎのきっかけとなり、後に否認対象行為となる個別の権利行使を促すという悪影響をあたえるものといえるでしょう。
速やかに申立てをし、受任通知を送らないことは、混乱を避け、依頼者の物理的・心理的な負担を回避するためにも有用です。
しかし、全ての法人で早期の申立てをしなければ財産の散逸が生じるわけではありません。
中小事業者では、依頼の時点で既に営業を停止しており、散逸したり劣化するような財産が存在しないことも多くあります。
それだけでなく、専門の経理担当者などもおらず、帳簿も調製されていないため、債務や財産の把握に時間を要することも多いでしょう。
このような場合に徒に早期の申立てを行ったとしても、正確性を欠き、却って破産管財人の管財業務を混乱させてしまう可能性もあります。ある程度時間をかけてでも状況を整理し、破産管財人に引き継ぐ方が有用な事案もあるといえます。
また、大阪地裁などでは申立前に賃借物件の明渡しを行うことで、予納金を低廉に抑えることが可能です。特に中小事業者では申立費用の捻出に苦労することも少なくありません。依頼者のためには、少し時間を要しても、明渡しを先行させることが有益でしょう(もっとも、この点については近時硬直的な運用も見られるところですので、いずれこのブログで触れたいと思います。)。
さらに、会社の保証人となっている代表者自身も破産申立てを行う場合、法人の申立てと同時に行えば、予納金を低く済ませることができる裁判所があります(いわゆる法人併存型。大阪地裁など。)。その準備期間を要する場合もあるでしょう。
こういった事案では、受任通知を送付したとしても、延滞状況下で取付け騒ぎには至っていないのですから弊害は少なく、むしろ債権者に情報提供することができるとともに、債権者が依頼者に接触することを牽制する利点があります。
なお、受任通知については、発送が当然であって必ず行わなければならないと誤解されていることがあります。これは、個人の同時廃止の破産申立てを主に行っている方が陥りやすい誤解でしょう。
同時廃止では債権調査票の提出を義務づけられている裁判所が多いことと、貸金業者の激烈な取立てを止めなければならなかったという歴史的経緯から、個人の同時廃止申立てでは受任通知を送ることが必須となっているだけです。
管財の申立てで、帳簿等から破産債権の存否・額を確認できるのであれば債権調査票は不要ですし、取立てを止めなければならない事情がなければ受任通知自体も必要ではありません。
もういちどまとめますと、申立代理人としては、早期の申立てを行うことや受任通知の発送の要否は、依頼者の利益の観点から考えなければならず、倒産秩序の維持もその文脈での考慮であって、それ自体が自己目的化するわけではない、といえます。